KNOWLEDGE & TOPICS ナレッジ&トピックス
ナレッジ&トピックス
合併には、吸収合併と新設合併とがありますが、吸収合併存続会社、吸収合併消滅会社、新設合併消滅会社の手続きは、原則として以下のようになります。
また、新設合併の新設会社についても、同様の手続きになりますが、新たに設立される会社のため債権者保護手続や株主への通知は不要となります。
取締役会において合併承認決議を経て、被合併と合併契約を締結します。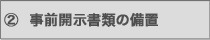
開示書類は、
①株主総会決議の日の2週間前の日
②株主に対する買取手続の通知又は公告の日
③債権者に対する公告又は個別催告通知の日
のうちいずれか早い日から開始し、効力発生日後6カ月間備置しなければなりません(会社法第794条第2項)。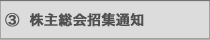
株主総会の2週間前までに発送する必要があります(会社法第299条第1項)。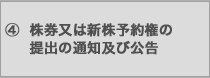
【効力発生日の1か月間以上前に公告及び通知】
消滅会社が株券又は新株予約権発行会社である場合には、効力発生日の1カ月前までに、株券又は新株予約権の提出に関する公告を行い、かつ、株主及びその登録株式質権者又は新株予約権者及び登録新株予約権質権者には通知しなければなりません(会社法第219条第2項6号、同第293条第1項3号)。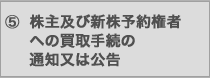
【効力発生日の20日前まで】
合併に反対する株主に対して、株式の買取請求が認められています。そのための通知又は公告を株主に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第797条第3項、第4項)。
消滅会社の新株予約権者に対して新株予約権の買取請求の機会を与えるため、通知又は公告を新株予約権者に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第787条第3項、第4項)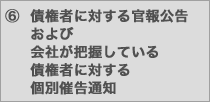
【1カ月以上の異議申立期間】
原則として、債権者保護手続は、合併する旨及び両社の最終事業年度に係る決算公告の開示情報を記載した公告文を官報に掲載し、かつ会社が把握している債権者に対して、公告と同内容の情報を文書で個別催告する必要があります。
また、官報公告掲載日及び個別催告日の翌日から1ヶ月以上の異議申述期間を設ける必要があります。(会社法第799条第2項)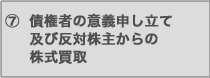

【効力発生日の前日まで】
株主総会の特別決議による承認が必要となります(会社法第309条第2項)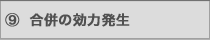
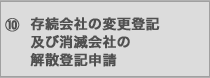
登記を行うことにより、第三者対抗要件が具備されます。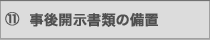
効力発生日から6カ月間、承継した消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項を記載した書面を作成し、本店に備置しなければなりません(会社法第801条第1項、第3項)。
(注)参照条文は、吸収合併存続会社の条文になります。
合併契約書には、記載しなければならない事項が法定されています(会社法第749条)。
(1) 存続会社及び消滅会社の商号および住所(同条第1項第1号)(2) 消滅会社の株主に対して存続会社の株式を交付する場合には、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法(同条第1項第2号イ)(3) 存続株式会社の増加する資本金及び準備金の額(同条第1項第2号イ)(4) 合併の効力発生日(同第6号)
また、法定記載事項の以外に、任意事項を定めることができます(任意的記載事項)。
任意的記載事項としては、実務上以下のような事項を定めておくことが考えられます。
(1) 定款変更に関する事項(商号、目的、公告方法、発行可能株式総数など)(2) 各会社が合併の日までに剰余金の配当を行うときはその限度額(3) 合併に際して就職すべき取締役・監査役(4) 退任役員に対する退職慰労金の支給に関する事項(5) 合併契約の解除条項
分割には、吸収分割と新設分割とがありますが、吸収分割承継会社、吸収分割会社、新設分割会社の手続きは、原則として以下のようになります。
また、新設分割の新設会社についても、同様の手続きになりますが、新たに設立される会社のため債権者保護手続や株主への通知は不要となります。
取締役会において合併承認決議を経て、被合併と合併契約を締結します。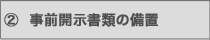
開示書類は、
①株主総会決議の日の2週間前の日
②株主に対する買取手続の通知又は公告の日
③債権者に対する公告又は個別催告通知の日
のうちいずれか早い日から開始し、効力発生日後6カ月間備置しなければなりません(会社法第794条第2項)。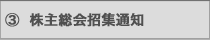
株主総会の2週間前までに発送する必要があります(会社法第299条第1項)。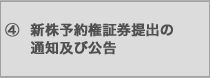
【効力発生日の1か月間以上前に公告及び通知】
消滅会社が新株予約権証券を発行しており、その新株予約権に代えて承継会社となる会社の新株予約権が交付されると定められている場合は、効力発生日の1カ月前までに、新株予約権証券の提出に関する公告を行い、かつ、新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には通知しなければなりません(会社法第293条1項第4号、5号)。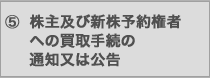
【効力発生日の20日前まで】
会社分割に反対する株主に対して、株式の買取請求が認められています。そのための通知又は公告を株主に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第797条第3項、第4項)。
消滅会社の新株予約権者に対して新株予約権の買取請求の機会を与えるため、通知又は公告を新株予約権者に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第787条第3項、第4項)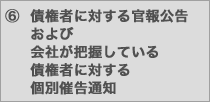
【1カ月以上の異議申立期間】
原則として、債権者保護手続は、分割する旨及び両社の最終事業年度に係る決算公告の開示情報を記載した公告文を官報に掲載し、かつ会社が把握している債権者に対して、公告と同内容の情報を文書で個別催告する必要があります。
また、官報公告掲載日及び個別催告日の翌日から1ヶ月以上の異議申述期間を設ける必要があります。(会社法第799条第2項)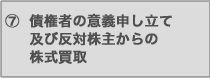

【効力発生日の前日まで】
株主総会の特別決議による承認が必要となります(会社法第309条第2項第12号)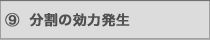
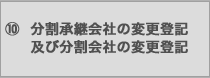
登記を行うことにより、第三者対抗要件が具備されます。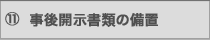
分割会社及び承継会社は、効力発生日から6カ月間、吸収分割により承継会社に移転した分割会社の重要な権利義務に関する事項その他会社分割に関する重要事項を記載した書面を作成し、本店に備置しなければなりません(会社法第801条第1項、第3項)。
株式交換の会社法上の手続きは、原則として以下のようになります。
取締役会において株式交換承認決議を経て、被合併と合併契約を締結します(会社法第767条)。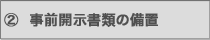
開示書類は、
①株主総会決議の日の2週間前の日
②株主に対する買取手続の通知又は公告の日
③債権者に対する公告又は個別催告通知の日
のうちいずれか早い日から開始し、効力発生日後6カ月間備置しなければなりません(会社法第794条第2項)。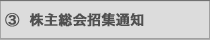
株主総会の2週間前までに発送する必要があります(会社法第299条第1項)。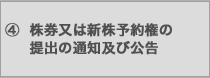
【効力発生日の1か月間以上前に公告及び通知】
株式交換に当たって完全子会社となる会社が株券又は新株予約権発行会社である場合には、効力発生日の1カ月前までに、株券又は新株予約権の提出に関する公告を行い、かつ、株主及びその登録株式質権者又は新株予約権者及び登録新株予約権質権者には通知しなければなりません(会社法第219条第1項7号、同第293条第1項6号)。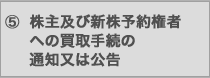
【効力発生日の20日前まで】
株式交換に反対する株主に対して、株式の買取請求が認められています。そのための通知又は公告を株主に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第797条第3項、第4項)。
完全子会社となる会社の新株予約権者に対して新株予約権の買取請求の機会を与えるため、通知又は公告を新株予約権者に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第787条第3項、第4項)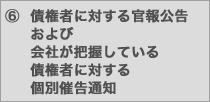
【1カ月以上の異議申立期間】
原則として、債権者保護手続は、株式交換をする旨及び両社の最終事業年度に係る決算公告の開示情報を記載した公告文を官報に掲載し、かつ会社が把握している債権者に対して、公告と同内容の情報を文書で個別催告する必要があります。
また、官報公告掲載日及び個別催告日の翌日から1ヶ月以上の異議申述期間を設ける必要があります。(会社法第799条第2項)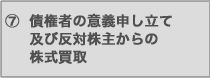

【効力発生日の前日まで】
株主総会の特別決議による承認が必要となります(会社法第309条第2項)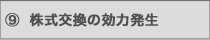

登記を行うことにより、第三者対抗要件が具備されます。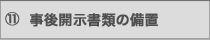
完全子会社となった会社は、効力発生日から6カ月間、株式交換の効力発生日、株式移転完全子会社における株式買取請求手続及び債権者異議手続の経過 及びその他の株式交換に関する重要な事項を記載した書面を作成し、本店に備置しなければなりません(会社法第801条第3項、791条第1項2号)。
株式移転の会社法上の手続きは、原則として以下のようになります。
株式移転をするためには、少なくとも会社法第773条にて規定された事項を定めた株式移転計画を作成する必要があります(会社法第772条)。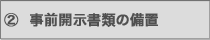
株式移転により完全子会社となる会社は、事前開示書類を
①株主総会決議の日の2週間前の日
②株主に対する買取手続の通知又は公告の日
③債権者に対する公告又は個別催告通知の日
のうちいずれか早い日から、効力発生日後6カ月間備置しなければなりません(会社法第803条第1項3号)。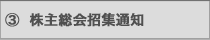
株主総会の2週間前までに発送する必要があります(会社法第299条第1項)。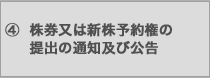
【効力発生日の1か月間以上前に公告及び通知】
株式移転に当たって完全子会社となる会社が株券又は新株予約権発行会社である場合には、効力発生日の1カ月前までに、株券又は新株予約権の提出に関する公告を行い、かつ、株主及びその登録株式質権者又は新株予約権者及び登録新株予約権質権者には通知しなければなりません(会社法第219条第1項8号、同第293条第1項7号)。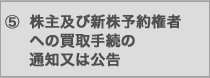
【効力発生日の20日前まで】
株式移転により完全子会社となる会社は、反対する株主に対して、株式の買取請求が認められています。そのための通知又は公告を株主に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第806条第3項、第4項)。
完全子会社となる会社の新株予約権者に対して新株予約権の買取請求の機会を与えるため、通知又は公告を新株予約権者に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第808条第3項、第4項)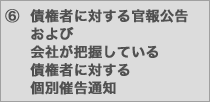
【1カ月以上の異議申立期間】
原則として、債権者保護手続は、株式移転をする旨及び消滅会社の最終事業年度に係る決算公告の開示情報を記載した公告文を官報に掲載し、かつ会社が把握している債権者に対して、公告と同内容の情報を文書で個別催告する必要があります。
また、官報公告掲載日及び個別催告日の翌日から1ヶ月以上の異議申述期間を設ける必要があります。(会社法第810条第2項)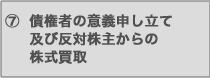

【効力発生日の前日まで】
株主総会の特別決議による承認が必要となります(会社法第309条第2項)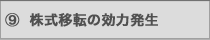
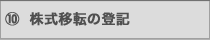
登記を行うことにより、第三者対抗要件が具備されます。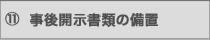
完全子会社となった会社は、効力発生日から6カ月間、株式移転の効力発生日、株式移転完全子会社における株式買取請求手続及び債権者異議手続の経過 及びその他の株式移転に関する重要な事項を記載した書面を作成し、本店に備置しなければなりません(会社法第811条第1項2号、第2項)。
会社法第773条においては、株式移転計画において定める事項として、以下の1から10があります。
1.完全親会社となる新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2.上記1のほか、完全親会社となる新設会社の定款で定める事項
3.完全親会社となる新設会社の設立時取締役の氏名
4.(a) 完全親会社となる新設会社が会計参与設置会社である場合、設立時の会計参与の氏名、又は名称
(b) 完全親会社となる新設会社が監査役設置会社である場合、設立時の監査役の氏名
(c) 完全親会社となる新設会社が会計監査人設置会社である場合、設立時の会計監査人の氏名又は名称
5.株式移転に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる新設会社の株式に関する事項(その数、算定方法、完全親会社となる新設会社の資本金及び準備金の額)
6.完全子会社となる会社の株主に対する上記5の割当てに関する事項
7.株式移転に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる新設会社の社債に関する事項(その種類、金額等)
8.完全子会社となる会社の株主に対する上記7の割当てに関する事項
9.株式移転に際して、完全子会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代わり交付する完全親会社となる新設会社の新株予約権に関する事項(その内容、数、算定方法等)
10.完全子会社となる会社の新株予約権者に対する上記9の割当てに関する事項
事業譲渡における会社法上の手続きは、原則として以下のようになります。
ただし、事業譲渡する相手方が事業譲渡をする会社の特別支配会社である場合には、株主総会の決議は不要とされています(会社法第468条第1項)。ここで、特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(ないしこれを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を保有している場合の当該会社(支配株主会社)のことをいいます。
事業譲渡は、取引法上の行為であるため、譲渡する資産・負債が当然に譲受会社に引き継がれることはなく、個別の資産や契約上の権利・義務ごとに対抗要件の具備や権利移転行為が必要となります。
取締役会において事業譲渡承認決議を経て、被合併と合併契約を締結します。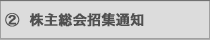
株主総会の2週間前までに発送する必要があります(会社法第299条第1項)。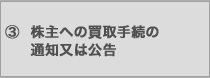
【効力発生日の20日前まで】
事業譲渡に反対する株主に対して、株式の買取請求が認められています。そのための通知又は公告を株主に対して効力発生日の20日前に行う必要があります(会社法第469条第3項)。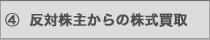

【効力発生日の前日まで】
譲渡会社では、株主総会の特別決議による承認が必要となります(会社法第309条第2項)
譲受会社では、全事業の譲受の場合には、株主総会の特別決議による承認が必要となります(同条同項)。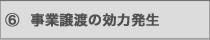
現物出資の手続きは、通常の新株発行の場合の手続きと基本的な流れは同じになります。現物出資は金銭以外の財産の出資のため、その財産的な裏付けがあるかどうかを調査することが求められ、原則として裁判所が選任した検査役の調査が必要となります。
ただし、次の場合は検査役による調査が不要とされています。
① 現物出資をする引受人に割り当てる募集株式の総数が発行済株式の総数の10分の1を超えない場合② 募集事項として決定された現物出資の目的となる財産の価額の総額が500万円を超えない場合③ 現物出資の目的とする財産が市場価格のある有価証券である場合において、募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が当該有価証券の市場価格を超えない場合④ 募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が相当であることについて、弁護士又は弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む)、監査法人、税理士又は税理士法人が証明した場合(財産が不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価が必要)⑤ 現物出資の目的とする財産が募集株式の発行をする株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であって、当該金銭債権に関する募集事項として決定された「現物出資の目的となる財産の価額」が、その金銭債権の帳簿価額を超えない場合